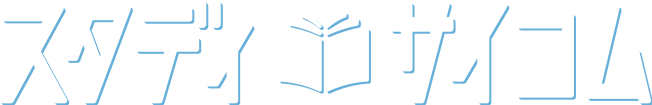さて、みなさん、大学入試は何のためにあるのか、お考えになったことはありますか。多くの方にとっては遠い昔の話でしょうが、受験勉強に明け暮れていたときには、誰だって、ふと、そんなことを考えたことはあるのではないでしょうか。
三角関数や微分・積分(どちらも高校で習う数学の単元)を勉強して、何のためになるのか。大学入試が終わったら、一生、そんなものが役に立つことはない。丸暗記した化学式も細胞の構造も世界史の年表も古文の単語も、そんなもの知らなくたって、社会に出てからたまに恥ずかしい思いをすることはあったとしても、困ることはないはずだ。なのに、大学受験があるから勉強しなくちゃならない。多くの人がそんな状況に疑問を持ったり、理不尽を感じたりしたことがあると思います。
私は数学者ですから、いやいや、そんなことはありません。数学って美しくて魅力に溢れていますと、声を大にして訴えたいところですけれど、「社会に出てから三角関数を知っていると何か役に立つことがありますか」と訊かれても、困ってしまいます。
では、なぜ、社会に出てからさして役に立たないようなことばかり教えて、それをどのくらい習得しているか、大学入試で試しているのでしょうか。
日本で近代社会が成立した明治時代以降、文部省や、大学の先生たちが何を考えて今の大学入試制度を作り上げてきたのかは別として、大学入試にははっきりとした機能があります。「当たり前じゃん」と言われそうですが、それは学生のスクリーニング(ふるいにかけること)です。ホワイトカラー(背広、ネクタイ姿で仕事をする人。事務職。)として社会に送り出すとき、この学生はどの程度の能力があるのか。その能力を測る指標として大学入試は機能しています。
学歴社会と言います。最近は、理系については修士課程で専門的な知識や技能を身につけている人材が優遇されるようになっていますが、文系の場合は大学院に行ったほうが就職率がかえって悪くなる。つまり、ホワイトカラーを代表する事務職を担う文系人材については、企業は大学や大学院での専門教育を重視していないということです。欧米や中国では、高級官僚は少なくとも修士かMBA、多くは博士を取得しているのとは対照的です。企業が文系人材の採用で重視しているのは、「大学入試をきちんと突破した」ことなのです。
三角関数や微分・積分は、一部の専門職業を除き仕事には役に立ちませんが、それを理解できる能力や、理解はできないまでも公式を憶えて問題を解ける能力は、仕事でも有効で汎用性があります。他の科目も同じです。世界史の年表を暗記する力や、記述式の問題に解答できる能力には汎用性があるのです。もちろん例外はありますが、人事採用の経験上、偏差値の高い大学に入学できる学力がある人ほど、仕事でも能力を発揮する可能性が高いことが多かったため、大学入試が社会システムとして定着してきたのです。また、自分の役に立つかどうかもわからないことでも、やれと言われれば一生懸命に取り組む従順性や、入試のためだからと割り切って努力できる合理性は、企業が多くの従業員に求める資質だと考えることもできます。国や大学の側が意識的にそう考えて大学制度や入試制度を設計してきたかどうかはともかく、企業の側は、大学入試のそのような機能を見抜いて、出身大学を就職希望者のスクリーニングに使ってきました。
出典『AI VS. 教科書が読めない子どもたち』(新井紀子著 東洋経済)